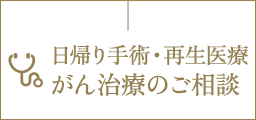2025年8月にボクシングの興行で2選手が急性硬膜下血腫によって死亡しました。お亡くなりになられたのは東洋太平洋・日本スーパーフェザー級5位にランクされていた神足茂利さんと、日本ライト級挑戦者決定8回戦に出場した浦川大将さん。いずれも試合直後に発症し、開頭手術をうけたものの、意識は回復せずに数日後、息を引き取りました。このほか、同月にアマチュアボクシング登録している競技者が練習後に救急搬送され、急性硬膜下血腫のため開頭手術を受けてICUに入っているというニュースも流れました。
そもそも「急性硬膜下血腫」とはどのような症状なのでしょうか。ここでは急性硬膜下血腫のメカニズムや処置方法、その後の後遺症治療などについても解説していきます。
<コラム監修者>

田中聡(たなか さとし)
表参道総合医療クリニック院長
大阪医科大学医学部卒業。救急車搬送が日本で一番多い「湘南鎌倉総合病院」や「NTT東日本関東病院」にて脳神経外科医として脊椎・脊髄疾患、脳疾患、がん患者の治療に従事。その後、稲波脊椎関節病院で脊椎内視鏡、森山記念病院で脳・下垂体の内視鏡の経験。様々な患者様を診療するようになりました。しかし、脳出血や脳梗塞の方は、手術をしても脳機能自体は回復しないため、麻痺は改善しません。また腰痛が改善しなかったり、手術後も痛みやしびれが残る後遺症に悩まされている患者様を見てきて、「現代の医療では解決できない問題を治療したい」と表参道総合医療クリニックを開院しました。開院後、多数の腰痛日帰り手術や、再生医療などを行い、多方面から高い評価をいただいています。
┃1.脳卒中に対する再生医療について
急性硬膜下血腫とは、交通事故や転倒などの強い衝撃が原因で、脳を覆う硬膜と脳の間が出血し、急速に血液が溜まってしまう病気です。血液が脳を強く圧迫してしまうため、命に関わる危険性もあります。
発症直後から意識障害や瞳孔の左右差などが見られ、緊急手術によって血液による脳圧迫を除去しなければいけません。
<硬膜とは>
脳と脊髄は3層の髄膜に覆われています。脳の周りの髄膜は頭蓋骨と脳の間にあり、脳や脊髄を物理的な衝撃や感染から保護する役割を担っています。そのほか、脳脊髄液の流れを調整することで、脳への栄養供給にも関与しています。
その3層の髄膜のうち、一番外側にある丈夫な膜が「硬膜」です。
┃2.急性硬膜下血腫の対応
急性硬膜下血腫になると、少しでも早く対処することが大切です。症状が見られたらすぐに救急車を呼びましょう。
【主な症状】
- 意識障害:事故直後だけでなく、時間の経過とともに意識が遠のいていく場合もあります。
- 瞳孔の左右差:片方の瞳孔だけ大きく開いたり、両目ともに瞳孔が開いたままになってしまうことがあります。
- 半身麻痺:体の片側が麻痺して思うように動かなくなることがあります。
搬送後には、脳へのダメージを最小限に留めるため緊急手術が行われます。多くが頭を開けて血液による脳の圧迫を取り除く「開頭血腫除去術」が行われますが、そのほかドリルで頭蓋骨に穴を明けて、そこから血腫を吸引する「穿頭血腫ドレナージ術」という術式もあります。術後は脳の腫れが酷かったり、脳組織がすでに破壊されている場合、脳への圧迫を軽減するため、頭蓋骨を一時的に外しておくこともあります。
なお、急性硬膜下血腫の一般的な死亡率は5割以上とされています。
┃3.急性硬膜下血腫による後遺症
急性硬膜下血腫は直接脳細胞にダメージを与えてしまう病気です。圧迫などにより破壊された脳細胞は自然に回復することはないため、症状から回復したとしても重い後遺症を伴うことも少なくありません。
主な後遺症は下記の通りです。
<運動障害>
手足が思うように動かなくなったり、体の半身が麻痺したりします。このほか、歩行時にふらついたり、転倒しやすくなることもあります。
<言語障害>
言葉がすぐに出てこなかったり、呂律がうまく回らなかったりします。
<認知機能障害>
記憶力や集中力、判断力の低下などが起こります。これにより、物忘れが酷くなる傾向が見られます。
<高次脳機能障害>
記憶力や集中力、判断力の低下などが起こります。これにより、物忘れが酷くなる傾向が見られます。
<意識障害>
症状が重度だった場合、意識レベルの低下が後遺症として残ってしまうこともあります。
┃4.後遺症治療について
後遺症の治療は、理学療法士などによるリハビリテーションで行われます。しかし残った麻痺や障害などの根本原因である脳細胞の損傷については、脳細胞の再生ができないため、治療が難しいとされてきました。
しかし、近年は再生医療の研究が発展しており、「幹細胞」を使った治療であれば修復不可とされてきた脊髄や神経細胞を修復できる可能性が示唆されています。
<幹細胞治療とは>
幹細胞は身体の修復や再生が必要なときに自ら細胞分裂を行い、傷ついたり不足した細胞の代わりとなる細胞です。体の修復能力を持つので、これまで難しかったとされる症状も治すことができると注目を集めています。
幹細胞は分裂して同じ細胞を作る能力を持った「組織幹細胞」と「多能性幹細胞」の2種類に分けられます。組織幹細胞の中でも間葉系幹細胞は骨髄や脂肪、歯髄、へその緒、胎盤などの組織に存在する体性幹細胞の一種で、さまざまな細胞へ分化することができます。
患者自身の体から採取した脂肪細胞をもとに幹細胞を培養。それを患部に投与することで、神経細胞の修復を試みます。
副作用:脂肪採取部位・注射部位の腫れや痛み、感染
料金:片側1部位:1部位(片側)1,650,000円、2部位(両側)2,200,000円(税込)
※自費診療です
>>幹細胞治療について詳しくはこちら
┃5.再生医療のメリットとデメリット
幹細胞治療はさまざまなメリットがある一方、新しい治療であるためリスクも存在します。
<メリット>
- 患者さん自身の細胞を使っているので安全性が高いです
- 副作用があまりありません
- 今まで対応が難しかった症例でも、根本的な治療ができる可能性があります
- 入院の必要は、外来で治療をすることができます
<デメリット>
- 自由診療のため保険は適応されません
- 新しい治療法のため、長期での体への影響が確認されていません
- 患者さん自身の再生力を利用した治療法なので、効果が現れるまで個人差があります
┃6.まとめ
これまで治療が難しいとされていた症例も、近年では再生医療の研究が進展したことによって新しい選択肢が増えてきています。「もう根本的な治療は難しい」と諦めていた方も、まずはお気軽にご相談ください。
【関連記事】
・「再生医療」って何?使用される幹細胞や効果的な疾患を詳しく解説
・脳出血の後遺症に効果がある再生医療とは?幹細胞治療について解説
・「脊髄出血」とは?くも膜下出血や硬膜外血腫などの初期症状と再生医療による後遺症治療
┃YouTubeでも医療知識を紹介しています
今回の内容はYouTubeでも田中院長がお話ししています。そのほかにも様々ありますので、ぜひご覧ください。



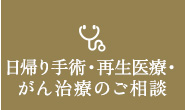




 東京メトロ
東京メトロ クリニック前にパーキング
クリニック前にパーキング