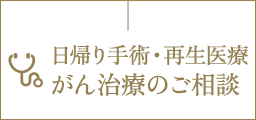スポーツ選手にとって、常に隣り合わせなのが怪我。ケアをしっかりしていたとしても、激しくぶつかり合ったり、過酷な練習で靭帯や骨が損傷してしまう可能性は十分あります。靭帯などは手術が一般的な治療法ですが、復帰までに時間がかかってしまうデメリットもあり、早期復帰したい選手にとっては手術をするか、痛みに耐えてプレーすのか悩ましい問題です。ここでは、手術なしで損傷部位の修復効果が期待できる治療の選択肢「PRP治療」について解説します。
<コラム監修者>

田中聡(たなか さとし)
表参道総合医療クリニック院長
大阪医科大学医学部卒業。救急車搬送が日本で一番多い「湘南鎌倉総合病院」や「NTT東日本関東病院」にて脳神経外科医として脊椎・脊髄疾患、脳疾患、がん患者の治療に従事。その後、稲波脊椎関節病院で脊椎内視鏡、森山記念病院で脳・下垂体の内視鏡の経験。様々な患者様を診療するようになりました。しかし、脳出血や脳梗塞の方は、手術をしても脳機能自体は回復しないため、麻痺は改善しません。また腰痛が改善しなかったり、手術後も痛みやしびれが残る後遺症に悩まされている患者様を見てきて、「現代の医療では解決できない問題を治療したい」と表参道総合医療クリニックを開院しました。開院後、多数の腰痛日帰り手術や、再生医療などを行い、多方面から高い評価をいただいています。
◆目次
1.PRP療法とは
2.スポーツ選手も治療に使うPRP
3.主なスポーツ外傷について
4.PRP療法のメリットと注意点
5.当院のPRP療法の流れと費用
6.PRPと併用したい「幹細胞治療」
7.まとめ
┃1.PRP療法とは
PRP(Platelet-rich plasm)とは、日本語に訳すと多血小板血漿(たけっしょうばんけっしょう)といって、血小板を濃縮させたものです。血小板にはさまざまな効果をもたらす細胞で、周りの細胞に働きかけて組織の修復を促す働きを持っています。この作用を利用したのが、患者さん自身の血液を使って行う「PRP療法」。患者さんから採血を行った後、採取した血液から血小板を抽出・濃縮し、それを患部に注射して、損傷している組織の修復を促します。
また炎症を抑える作用も期待できるため、痛みを軽減する効果も見込めます。
┃2.スポーツ選手も治療に使うPRP
スポーツをしていると、普段の生活では使わないような特殊な動きが多く出てきます。一部の関節に負荷がかかったり、身体を不自然にねじったりという動きによって怪我を負ってしまうことも少なくありません。
特に靭帯や骨などに関わる怪我は、手術が必要になる場合も。しかし、手術後に最盛期のパフォーマンスが戻るかと言われると100%戻るとは言い切れません。また手術後の回復期間も長くなってしまうので、復帰まで時間がかかってしまいます。学生で部活動をしている選手や、プロスポーツ選手にとっては、「今結果を出さないと」「この時期までに治さないと」などという悩みはつきもの。いつ手術に踏み出すのか、どの時期から本格的に治療に取り組むのかという問題は重要なのです。
そこで注目を集めているのがPRP療法。特に海外では10年以上の実績があり、多くのスポーツ選手が治療方法に採用しています。治療後に療養期間を取らなくても大丈夫なので、シーズン中であれば一度、PRP療法を試して、そこから手術を考えるという選手もいます。
2014年、当時ニューヨークヤンキースに所属していた田中将大選手に右肘靭帯の部分断裂が判明。通称トミー・ジョン手術と呼ばれる「靱帯再建手術」で治療をするのが一般的ですが、球団はPRP療法を選択。怪我が発覚した7月から、治療と地道なリハビリを経て9月に復帰登板を果たしました。その後もトミー・ジョン手術は行っていません。
2018年6月には、エンゼルスの大谷翔平選手が右肘の内側側副靱帯を損傷。PRP療法を受けて、翌月には打者として復帰しています。ただし、同年10月にはトミー・ジョン手術を受け、約1年後に投手としても復帰しています。
┃3.主なスポーツ外傷について
野球以外にも、スポーツの動きによって様々な症状が出る可能性があります。ここではPRP療法で修復作用促進効果の見込めるスポーツの怪我を紹介します。
<野球肘>
投球動作で肘に繰り返し負担がかかると、負荷がかかっているところにダメージが起きてしまいます。ポジション別で見ると、一番患者数が多いのが投手、次に捕手、さらに外野手と続きます。内野手もサードやショートなどの強い球を投げる運動を繰り返すポジションで、肘に負担がかかるフォームで投げていると、野球肘を発症する場合があります。また正式な疾患名称は、損傷が起きている部位によって変わります。
また小学生から高校生は、肘が未熟であるため、頻出する傾向にあります。
<テニス肘>
正式には「上腕骨外側上顆炎」といって、手首を曲げる、手で強くものを握るなどといった繰り返しの動作が原因で、肘の外側に痛みが生じます。テニス以外の競技者や、フライパンを振る料理人など、同様の動きを伴うものであれば、発症する可能性があります。
<ゴルフ肘>
正式名称は「上腕骨内側上顆炎」といって、スナップを効かせるように手首を内側に曲げる動作や、物を持ったまま肘を曲げる動作を繰り返すことで発症するスポーツ障害です。上腕骨内側上顆にくっついている腱が炎症を起こしてしまい痛みが発生します。日常生活でも見られる動作なので、競技者ではなくても発症することがあります。
┃4.PRP療法のメリットと注意点
PRP療法にはさまざまなメリットがありますが、注意点もあります。リスクも押さえた上で、適した治療法を検討しましょう。
<PRP療法のメリット>
- 自分の血液からPRPを抽出するため、アレルギーや拒絶反応のリスクが低い
- 手術や入院が不要なので、外来で行うことができる
- さまざまな疾患に対して効果が期待できる
- 治療に年齢などの制限がない
<注意点・リスク・限界>
- 患者自身の再生力を利用した治療法なので、効果の程度や期間には個人差がある
- 自由診療のため保険が適応されない
- 新しい治療法のため、長期での体への影響が確認されていない
┃5.当院のPRP療法の流れと費用
当院では、患者さんお一人おひとりの状態や生活スタイルに合わせ、適切な治療法をご提案します。ここでは、当院のPRP療法の流れと費用を紹介します。
<当院のPRP療法の流れ>
当院では、以下のような流れでPRP療法を行います。
【診察・カウンセリング】
診察や検査で膝の状態を確認し、PRP療法が適しているか判断します。
【採血・PRPの精製】
患者さんの血液を採取し、遠心分離機を用いて血小板を濃縮したPRPを精製します。
【PRPの注射】
患部にPRPを注射します。採血から注射まで30分程度で終わり、その日のうちにご帰宅いただけます。
<費用>
PRP療法は保険適用外(自由診療)です。当院では、以下の費用で腰痛に対するPRP療法を行っています。
【参考】シングル膝(2V):330,000円
┃6.PRPと併用したい「幹細胞治療」
再生医療はPRPだけではありません。当院では患者様ご自身の体から採取した脂肪細胞をもとに幹細胞を培養し、幹部に注射することで組織の回復を図るASC治療という幹細胞治療を行っております。脂肪由来幹細胞(Adipose-derived Stem Cell)を用いた再生医療の一種で、発がん性のリスクが少ないことやご自身から接種したものなので副作用が少なく体への負担も少ないのが特徴です。
┃6.まとめ
PRP療法は、自分自身の血液から抽出した成分を利用して組織の修復を助ける再生医療の一つです。スポーツ障害だけでなく、腰痛や膝など関節痛など、さまざまな疾患に効果が期待できます。手術を避けたい方や、一般的な治療で十分に症状が改善しない方は、お気軽にご相談ください。
【関連記事】
・スポーツで負った怪我を早く治すことができる再生医療、スポーツ外傷についても詳しく解説
・40代男性「腰痛が酷くて大会に出られない」椎間板の損傷を再生医療『PDR(経皮的椎間板再生治療)』で治療した症例
・PRP療法って何?自分の血液から作る再生医療の選択肢
┃YouTubeでも医療知識を紹介しています
今回の内容はYouTubeでも田中院長がお話ししています。そのほかにも様々ありますので、ぜひご覧ください。



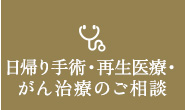




 東京メトロ
東京メトロ クリニック前にパーキング
クリニック前にパーキング