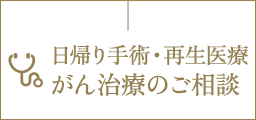ある日突然起こる病気の1つ「脊髄出血」。くも膜下出血などを指す病気で、一命をとりとめたとしても、後遺症に悩まされる人も少なくありません。病気を経験された方、またはご家族にとって、後遺症との向き合い方はとても大きな課題です。リハビリだけでは思うように改善が見られず、「もっと良くなる治療法はないのか?」「再生医療ってどこで受けられるの?」と疑問を抱えていませんか? この記事では脊髄出血に関する初期症状と、再生医療を使った治療について詳しく解説します。
<コラム監修者>

田中聡(たなか さとし)
表参道総合医療クリニック院長
大阪医科大学医学部卒業。救急車搬送が日本で一番多い「湘南鎌倉総合病院」や「NTT東日本関東病院」にて脳神経外科医として脊椎・脊髄疾患、脳疾患、がん患者の治療に従事。その後、稲波脊椎関節病院で脊椎内視鏡、森山記念病院で脳・下垂体の内視鏡の経験。様々な患者様を診療するようになりました。しかし、脳出血や脳梗塞の方は、手術をしても脳機能自体は回復しないため、麻痺は改善しません。また腰痛が改善しなかったり、手術後も痛みやしびれが残る後遺症に悩まされている患者様を見てきて、「現代の医療では解決できない問題を治療したい」と表参道総合医療クリニックを開院しました。開院後、多数の腰痛日帰り手術や、再生医療などを行い、多方面から高い評価をいただいています。
┃1.脊髄出血とは
脊髄出血とは、その名前の通り脊髄やその周囲の組織で出血が起きてしまう症状です。血管の異常や外傷などが原因となって、発症すると突然の痛みや麻痺、感覚障害などを引き起こします。
脊髄出血は、脊髄のどこで出血するかでさらに詳しい病名に分類されます。
<硬膜外血腫>
頭部を強く打った時に、頭蓋骨と脳を覆う硬膜(こうまく)の間で出血し、その血が溜まって血腫となった状態を指します。特に、急性硬膜外血腫は出血直後から数時間で急速に症状が悪化することがあります。緊急手術が必要となるケースもあります。
【出血部位】
脳と脊髄を覆う3層の髄膜のうち、一番外側にある丈夫な膜「硬膜」の外側。
【原因】
交通事故、転倒、スポーツ中の怪我などで、頭をぶつけたことによる外傷。多くは頭蓋骨の骨折を伴うことが多いです。
【症状】
- 頭痛:激しい頭痛を伴うことがあります
- 意識障害:意識がもうろうとしたり、昏睡状態に陥ることもあります
- 嘔吐:吐き気を催したり、嘔吐を繰り返してしまうことがあります
- 麻痺:うまく言葉が出てこないといった言語障害が起きたり、手足の麻痺が発生したりします
- 瞳孔不同:左右の瞳孔の大きさに差が生じることがあります
<硬膜下血腫>
頭の打撲などにより約1~2か月をかけて、硬膜と脳の間にじわじわと出血し、それが溜まって血腫となってしまう病気です。基本的には出血自体に気が付かない場合も多く、ゆっくりと症状が進行します。しかし、強い衝撃で外傷を負った場合は、急性硬膜下血腫を引き起こすこともあり、急速に症状が悪化する場合は緊急手術が必要となる場合もあります。
【出血部位】
脳と脊髄を覆う3層の髄膜のうち、一番外側にある丈夫な膜「硬膜」の内側と脳の間。
【原因】
交通事故、転倒、スポーツ中の怪我などで、頭をぶつけたことによる外傷。脳組織の損傷「脳挫傷」を伴うことが多いです。
【症状】
- 頭痛:激しい頭痛を伴うことがあります
- 麻痺:神経の圧迫などによる痛みやしびれを引き起こすことがあります
- 認知症のような症状:物忘れや、意欲の低下、性格の変化、反応の低下などが起こることがあります
- 行動障害:手足が動かしにくい、歩きずらいなどといった症状が起こることがります
- 言葉が出にくい:瞬間的に言葉が出てこなくなります
- 舌のもつれ:舌が動かしにくくなってしまうことがあります
- 尿失禁:尿意を我慢することができず、漏らしてしまうことがあります
<くも膜下出血>
脳と脊髄を覆う3層の髄膜のうち、くも膜と軟膜の間にある「くも膜下腔」に出血が起こる病気です。40歳以上の女性に発症頻度が高い傾向が見られ、死亡率も高い疾患です。もしも救命できたとしても、後遺症が残ってしまうことも多く、高次脳機能障害、言語障害、運動麻痺などに悩まされます。
【出血部位】
くも膜と軟膜の間にある「くも膜下腔」。
【原因】
多くの場合が、脳動脈瘤の破裂が原因とされています。脳動脈瘤とは、血管の一部がこぶのように膨らんだ状態のことで、血管の分岐点によく発見されます。未破裂の状態で見つかることも少なくなく、その場合は症状が見られないことがほとんどです。
【症状】
- 頭痛:突然、激しい頭痛に見舞われます
- 吐き気:急激な吐き気や、繰り返す嘔吐などの症状が出ます
- 意識障害:意識がもうろうとしてしまいます
- 痙攣:急に手足の痙攣がとまらなくことがあります
- 麻痺:手足が麻痺して、思うように動かなくなります
- 視覚異常:視力の低下や、視界の一部が消えて見えなくなる視野欠損、光過敏などが起こることがあります
<髄内出血>
脊髄の中に血液が流れ出てしまう病気です。出血によって脊髄が圧迫されるので、様々な神経症状が起こります。
【出血部位】
脊髄の中。
【原因】
交通事故や、転倒によって脊髄が損傷を受けてしまうことが考えられます。そのほか脊髄や、その内部にある血管に腫瘍が原因で出血することもあります。また血液をサラサラにする抗凝固薬の副作用や、原因不明の特発性髄内出血などの可能性もあります。
【症状】
- 麻痺:急激に手足の動きが悪くなることがあります。出血部位によっては、体を全く動かせなくなることもあります
- 感覚障害:痛みや温度などの感覚が鈍くなったり、全く感じなくなることがあります
- 排尿・排便障害:排尿や排便をうまくコントロールできなくなってしまいます
- 激しい痛み:背中や首などに激しい痛みを伴うことがあります
┃2.脊髄出血の後遺症
脊髄出血の場合、治療して一命を取り留めたとしても多くの患者さんが悩まされるのが後遺症。出血の部位や程度によって異なりますが、主に運動麻痺や感覚障害、排尿・排便障害などが現れます。
脊髄損傷の部位によっては両手、両足の運動機能が低下もしくは喪失してしまう「四肢麻痺」や、両下肢のみに運動麻痺が起こる「対麻痺」、めまい,動悸,不眠,顔の火照り,四肢の冷汗などが起こる「自律神経障害」などが発症する可能性もあります。
後遺症は脊髄の損傷や、出血が起きた周囲の神経細胞の損傷などによって起こるものです。これまで脊髄や神経細胞は修復が難しいと言われており、後遺症の治療にはリハビリテーションや装具療法などの対症療法が一般的でした。
しかし、近年は再生医療の研究が発展しており、「幹細胞」を使った治療であれば修復不可とされてきた脊髄や神経細胞を修復できる可能性が示唆されています。
<幹細胞治療とは>
幹細胞は身体の修復や再生が必要なときに自ら細胞分裂を行い、傷ついたり不足した細胞の代わりとなる未分化の細胞です。体の修復能力を持つので、これまで難しかったとされる症状も治すことができると注目を集めています。
幹細胞は分裂して同じ細胞を作る能力を持った「組織幹細胞」と「多能性幹細胞」の2種類に分けられます。組織幹細胞の中でも間葉系幹細胞は骨髄や脂肪、歯髄、へその緒、胎盤などの組織に存在する体性幹細胞の一種で、さまざまな細胞へ分化することができます。再生が困難とされていた神経や血管、免疫系にも作用すると言われており、損傷した脳神経の回復促進にも作用することがわかってきました。
当院の幹細胞治療では、患者自身の体から採取した脂肪細胞をもとに幹細胞を培養。それを静脈投与、脊髄腔内投与で患部に注入し、神経細胞の修復を試みます。
┃3.表参道総合医療クリニックの幹細胞治療の流れ
当院では、患者様自身の脂肪組織から幹細胞を取り出し、培養したうえで投与する治療を行っています。幹細胞治療を行う際には、主に下記のような流れで治療を進めていきます。
<①カウンセリング>
事前に服薬情報やMRI画像などをご用意していただいた上で、医師がカウンセリングを行います。体調や既往歴、服薬中の薬、リハビリ状況などを伺います。
<②検査>
感染症の有無を調べるための血液検査や、胸部のレントゲン検査、心電図検査などを行います。
<③脂肪採取>
腹部からごく少量の脂肪を採取します。入院などは不要な場合がほとんどです
<④幹細胞の培養>
脂肪細胞から幹細胞を分離、培養します。培養には約3週間を要します。
<⑤幹細胞の静脈内投与、局所投与>
培養した幹細胞を点滴、局所に投与します。
<⑥経過観察>
その後の効果について定期的に経過観察を行います。
┃4.治療費について
再生医療は保険適用外の自由診療となります。費用の一例は以下の通りです(すべて税込)。
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 医師による診察・カウンセリング | 11,000円 |
| 感染症検査(採血) | 11,000円 |
| 脂肪由来幹細胞点滴投与 | 1回165万円 |
| 脂肪由来幹細胞髄腔内投与 | 1回198万円 |
┃5.再生医療のメリットとデメリット
再生医療はさまざまなメリットがある一方、新しい治療であるためリスクも存在します。
<メリット>
- 患者自身の細胞を使っているので安全性が高く、副作用が少ないです
- 今までは対応が難しかった症例も根本的に治療ができる可能性があります
- 入院の必要がなく、外来で治療をすることができます
<デメリット>
- 自由診療のため保険が適応されません
- 新しい治療法のため、長期での体への影響が確認されていません
- 患者自身の再生力を利用した治療法なので、効果が現れるまでに個人差があります
┃6.まとめ
脊髄出血は、せっかく命が救われたとしても、その後の後遺症に悩まされることの多い病気です。これまではリハビリテーションなどしか対症療法がありませんでしたが、日々進められている研究により、後遺症がよくなる可能性が広がりつつあります。後遺症に悩まれている方がいましたらお気軽にご相談ください。



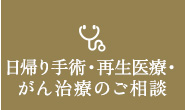




 東京メトロ
東京メトロ クリニック前にパーキング
クリニック前にパーキング