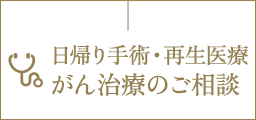糖尿病を患う多くの方が、血糖値のコントロールを続けながら生活を送っています。薬を服用し、食事療法や運動療法も継続している。それにもかかわらず、足のしびれ、視力低下、腎機能の悪化といった症状が現れることがあります。これは糖尿病による合併症の進行によって引き起こされているもので、従来の治療では「進行を遅らせる」ことはできても、「元に戻す」ことは困難でした。しかし現在は「再生医療」によって、神経や血管といった組織を再生し、合併症を根本的に改善する新たな選択肢が登場しています。今回は糖尿病による合併症について、従来の治療方法から再生医療を活用した方法まで詳しく解説します。
<コラム監修者>

田中聡(たなか さとし)
表参道総合医療クリニック院長
大阪医科大学医学部卒業。救急車搬送が日本で一番多い「湘南鎌倉総合病院」や「NTT東日本関東病院」にて脳神経外科医として脊椎・脊髄疾患、脳疾患、がん患者の治療に従事。その後、稲波脊椎関節病院で脊椎内視鏡、森山記念病院で脳・下垂体の内視鏡の経験。様々な患者様を診療するようになりました。しかし、脳出血や脳梗塞の方は、手術をしても脳機能自体は回復しないため、麻痺は改善しません。また腰痛が改善しなかったり、手術後も痛みやしびれが残る後遺症に悩まされている患者様を見てきて、「現代の医療では解決できない問題を治療したい」と表参道総合医療クリニックを開院しました。開院後、多数の腰痛日帰り手術や、再生医療などを行い、多方面から高い評価をいただいています。
◆目次
1.糖尿病の三大合併症とは
2.糖尿病は治すことは難しい?
3.合併症を発症した場合には
4.糖尿病に対する再生医療について
5.臨床研究における評価
6.当院の幹細胞治療の流れ
7.治療費について
8.再生医療のメリットとデメリット
9.まとめ
┃1.糖尿病の三大合併症とは
糖尿病は血液中のブドウ糖が増加してしまい、血管に負荷をかけてしまう病気です。高血糖を放置しておくと、心臓病や腎臓病、失明、足の切断などといった深刻な合併症を引き起こすリスクがあります。初期症状はほとんどなく、気が付いたら手遅れという場合も少なくありません。
疾患の原因として、お酒の飲み過ぎや運動不足、肥満などの生活習慣が大きく影響しているとされています。そのほか、遺伝子の異常や、妊娠によるホルモンバランスの変化から妊娠中に初めて発見される妊娠糖尿病などもあります。
糖尿病は全身の血管に作用するため、様々な病気の原因となることでも知られています。ここでは、糖尿病による合併症の中でも「糖尿病の三大合併症」と言われる病気について紹介します。
<糖尿病性網膜症>
糖尿病によって、血液中の血糖値がコントロールできなくなり数値が高い状態が続くと、特に細い血管が悪くなって問題が起こりがちです。眼球の内側にあって、眼底を覆う薄い膜である「網膜」も例外ではありません。高血糖が長く続くことで、血管障害が起こることを「糖尿病性網膜症」と言います。
網膜の細い血管が損傷すると網膜出血や網膜剥離などが起きて、視力が低下してしまいます。さらに進行すると失明する危険性もあります。
<糖尿病性腎症>
「糖尿病性腎症」とは、高血糖の状態が長く続くことで、血液をろ過する腎臓の「糸球体」という部分の血管が傷つき、ろ過機能が低下。尿にタンパクが漏れ出るようになる疾患です。高血糖を放置すると腎臓の動きは徐々に悪化し、最終的には人工透析が必要になることもあります。
<糖尿病性神経障害>
「糖尿病性神経障害」とは、糖尿病によって引き起こされる神経障害です。手足のしびれや感覚異常が生じ、重症化すると足が壊死した組織が乾燥したり感染してしまったりして腐敗してしまう「壊疽(えそ)」を起こしてしまい、足を切断しなければなりません。
┃2.糖尿病は治すことは難しい?
糖尿病の原因はインスリンを分泌する膵臓のβ細胞が何かしらの原因で破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなってしまうからです。膵臓は一度傷つくと治らないとされており、治療をすることは難しいとされてきました。そのため、これまでは高血糖にならないように薬を飲んだり、生活習慣を改善したりするのが一般的な治療でした。
下記では一般的な治療方法を解説します。基本的には「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の3つを組み合わせて血糖値をコントロール。完治させることは難しいので、合併症の進行を防ぐことを目的に行われます。
<食事療法>
バランスの取れた食事を適切な量で摂取することで、血糖値の急激な上昇を抑えます。糖質や脂質、塩分の過剰摂取を避け、食物繊維を積極的に摂るよう指導を受けることになります。糖尿病治療の基本であり、肥満の解消や防止のためにも行われます。
<運動療法>
運動はインスリンの効果を高めてくれる作用があるほか、血糖値を下げる効果も見込めます。ウォーキングや水泳、ジョギングなど無理なく継続できる方法を選ぶことが重要です。
<薬物療法>
食事療法、運動療法の2つを行っても数値が改善しない場合は、薬物を使って血糖コントロールを行います。薬の種類は経口血糖降下薬やインスリン注射など様々で、患者の状態に合わせて医師が処方します。
ただし糖尿病の中でも1型糖尿病の場合は、インスリン注射が必須となります。
┃3.合併症を発症した場合には
糖尿病による合併症を発症した場合、どんな合併症なのかによって治療方法が異なります。いずれも根本原因となっている糖尿病治療と同時進行で行われます。ただし、神経や腎臓など一度低下したり損傷した機能の回復が難しいとされる部位で合併症が起きることも多く、完治は難しいとされています。
<痛みやしびれなどの神経障害>
手足のしびれや、痛みなどが現れます。足のケアを入念に行うほか、必要に応じて薬物による治療を行います。
<網膜症など視力に関わる症状>
定期的な眼科健診を行い、視力の著しい低下がないか確かめます。そのほかレーザー治療や注射薬による治療が行われます。
<腎症など腎機能に関わる症状>
糖尿病によって腎機能が低下した場合、食事療法や薬物療法を行います。重症化している場合は透析療法が行われます。
<動脈硬化など血管が関わる症状>
高血糖によって血管が傷つきやすくなっているため、動脈硬化の恐れがあります。動脈硬化は脳卒中や心筋梗塞を引き起こすリスクが高いので、生活習慣の見直しはもちろん、血圧や脂質異常症の管理、薬物療法などが行われます。
┃4.糖尿病に対する再生医療について
再生医療とは、身体の組織や臓器を修復・再生することを目的とした医療です。中でも幹細胞治療は、体内の修復機能を担う幹細胞を活用し、傷ついた組織を再生することを目指します。
これまで糖尿病を根本的に治療することは難しいとされてきましたが、再生医療の研究の進展により、根本的な治療ができる可能性が高まっています。
<幹細胞治療とは>
幹細胞は身体の修復や再生が必要なときに自ら細胞分裂を行い、傷ついたり不足した細胞の代わりとなる未分化の細胞です。体の修復能力を持つので、これまで難しかったとされる症状も治すことができると注目を集めています。
幹細胞は分裂して同じ細胞を作る能力を持った「組織幹細胞」と「多能性幹細胞」の2種類に分けられます。組織幹細胞の中でも間葉系幹細胞は骨髄や脂肪、歯髄、へその緒、胎盤などの組織に存在する体性幹細胞の一種で、さまざまな細胞へ分化することができます。再生が困難とされていた神経や血管、免疫系にも作用すると言われており、損傷した脳神経の回復促進にも作用することがわかってきました。
当院の幹細胞治療では、患者自身の体から採取した脂肪細胞をもとに幹細胞を培養。それを静脈投与、脊髄腔内投与で患部に注入し、神経細胞の修復を試みます。
幹細胞には以下のような作用があると報告されています。
- 血管の新生を促す作用
- 慢性的な炎症を抑える作用
- 神経の保護や再生を促す作用
- インスリン感受性の改善など、代謝機能のサポート
これらの作用によって、糖尿病によって損傷した血管、神経、腎機能などの再生が期待されます。
┃5.臨床研究における評価
幹細胞治療は、これまで脳卒中や脊髄損傷、変形性関節症などの分野で研究が進められてきました。糖尿病に対する応用も進みつつあり、いくつかの研究で以下のような効果が報告されています。
- 血糖値やHbA1cの改善
- 感覚障害や疼痛の軽減
- 腎機能指標(クレアチニンや尿タンパク)の改善
- 下肢血流の改善と潰瘍の回復
┃6.当院の幹細胞治療の流れ
当院では、患者様自身の脂肪組織から幹細胞を取り出し、培養したうえで投与する治療を行っています。幹細胞治療を行う際には、主に下記のような流れで治療を進めていきます。
<①カウンセリング>
事前に服薬情報やMRI画像などをご用意していただいた上で、医師がカウンセリングを行います。体調や既往歴、服薬中の薬、リハビリ状況などを伺います。
<②検査>
感染症の有無を調べるための血液検査や、胸部のレントゲン検査、心電図検査などを行います。
<③脂肪採取・血液採取>
腹部からごく少量の脂肪を採取します。入院などは不要な場合がほとんどです。
<④幹細胞の培養・PRPの抽出>
幹細胞を使った治療の場合、脂肪細胞から幹細胞を分離、培養します。培養には約3週間を要します。PRP療法の場合、採血を行い、その後遠心分離機にかけて、PRP(多血小板結晶)を抽出します。
<⑤幹細胞・PRPの神経根局所投与、髄腔内投与>
培養した幹細胞や、抽出したPRPを脊髄の枝である神経根に局所投与もしくは髄腔内に投与します。
<⑥経過観察>
治療後の効果について定期的に経過観察を行います。治療効果を確認しながら、リハビリを併用します。
┃7.治療費について
再生医療は保険適用外の自由診療となります。費用の一例は以下の通りです(すべて税込)。
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 11,000円 |
| 血液検査 | 16,500円 |
| 自己脂肪由来間葉系幹細胞投与1回(1億個) | 1,650,000円 |
| 細胞保管費用(2年目以降) | 44,000円 |
┃8.再生医療のメリットとデメリット
幹細胞治療はさまざまなメリットがある一方、新しい治療なのでリスクも存在します。
<メリット>
- 患者自身の細胞を使っているので安全性が高く、副作用が少ないです
- 今までは対応が難しかった症例も根本的に治療ができる可能性があります
- 入院の必要がなく、外来で治療をすることができます
<デメリット>
- 自由診療のため保険が適応されません
- 新しい治療法のため、長期での体への影響が確認されていません
- 患者自身の再生力を利用した治療法なので、効果が現れるまでに個人差があります
┃9.まとめ
糖尿病の合併症は、「一度進行すると治らない」とされてきました。しかし、再生医療の研究が進んだことで「治す」あるいは「回復させる」ことが現実になりつつあります。これまでの治療で限界を感じていた方、将来の透析や失明への不安を抱えている方は、今までになかった治療の選択肢になるかもしれません。もしも気になった方はお気軽に当院にご相談ください。
【関連記事】
・Efficacy and safety of mesenchymal stem cell therapies for ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis.
Stem Cells Transl Med. 2024;13:886–897.
https://doi.org/10.1093/stcltm/szae040
・A review and meta‑analysis of stem cell therapies in stroke patients: effectiveness and safety evaluation.
Neurol Sci. 2024;45:65–74.
https://doi.org/10.1007/s10072-023-07032-z



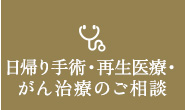




 東京メトロ
東京メトロ クリニック前にパーキング
クリニック前にパーキング